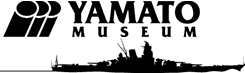今は大和ミュージアムの館長をさせていただいていますが、私は大学では彫刻を勉強していました。研究では有りません、造るほうです。今の仕事に入ったのは、物心付いたときから本が好きだったので、大学を出て、暫くしてから別の大学で図書館の勉強をして図書館司書の資格を取った事がきっかけでした。
美術大学の受験勉強は面白いもので、殆どデッサンばかりです。何しろデッサンが通らなければ、学科試験を受けられないのです。予備校の先生は、君たち勉強なんか適当で良いよ、自分の名前がチャンと書ければ良いよ。と真顔で言うような世界です。無論先生の言うことは守りました。
大学に入って、最初のオリエンテーションで、教授が出てきて、新入生をじろりと見回しました。私の大学は、多摩美術大学で、彫刻科の募集定員は、当時は年間15人(!)でしたが、私と同時に入ったのは1名少なく、14人でした。水増しと言うのは聞きますが、定員割れとは、実にさびしいクラスでした。
教授は、建畠覚造先生と、尾道に美術館がある、円鍔勝三先生でした。
建畠先生が、一息置いて、「君たち、彫刻科はね、学校創立以来求人は来たこと無いよ」と言って、ニヤッと笑って、「40歳,50歳になっても、アルバイトで暮らすようなことになるよ。人並みの暮らしがしたかったら、直ぐに他の大学に行きなさい」と言ったものです。その頃の私たちは、そんな先のことなんか真剣に考えるような気の利いた知恵の有るような人間ではありませんから、アハハと笑っていました。
彫刻の授業と言うのは、普通の勉強をしている学生には想像もつかないものです。なにしろ、1年生全員がまず、ガス溶接の免許を取らされます。授業では、鉄、木材、石、プラスチック、あらゆる物が素材として使われるので、まず何でも出来なくては作品が作れないのです。
例えば、ガス溶接、溶断、の手順を教わりますが、完全に記憶していても、思うように溶接が出来るわけでは有りません。何度も失敗しながら(ガスや溶接棒を散々無駄にしながら)たどたどしい作業をするのです。電気溶接は、楽だと思いました。私など、溶接用の濃いサングラスをしていたので、作業中チョット置いておいた溶接棒の、まだ赤く焼けているほうを、素手で掴んでしまい、酷い火傷をしたことがありました。
また、石彫をするときは、当時の生徒は、自分で石鑿を作ったものです。アトリエの隅に立派な鍛冶場が有り、そこで数本の鋼鉄の丸棒を焼き、金床で形を整え、焼入れするのです。助手の先生が教えてくれますが、同じようにやっても、先生の鑿は良く切れるのに、私の鑿は直ぐに先が丸くなってしまいます。だからと言って、焼きが堅すぎれば、刃先は直ぐに割れてしまうのです。ここでも、随分火傷しながら練習しました。木彫の鑿や切り出し小刀も、自分で研ぎます。だんだん良い砥石が欲しくなり、砥石屋に行きましたが(当時東京には砥石専門店が数軒ありました)良い天然の仕上げ砥は、自動車が買えるほど高価なので驚きました。私は、アルバイトを2か月して、その給料で、手ごろな砥石を一本買いました。大事に使ったものです。
こういった教育を受けて、何を思ったかと言うと、教育と訓練は違う、と言うことでした。原理原則はチャンと教えてもらわなくてはなりません、また、きちんとした基礎的な知識は必要です。しかし、モノの作り方を知っていても、知っている通りにモノを作り上げるには、知識とは別の訓練が必要なのです。
そして、この訓練は、必ず一定の時間は必要なのです。要領よく短時間で、と言うことは出来ないのです。私は、さっぱり切れない鑿をたたきながら、昔は、彫り物職人ばかりではなく、あらゆる職人の弟子に入るのは、普通123歳だったことを思い、そうだろうなー、20歳前後で修行を始めるのでは、手遅れなんだなあ・・。と思ったものです。
円鍔先生に、そう言うと、昔の人間は早死にだから、早くから修行するのだよ、戸高君は今が12歳だと思えば良いのだよ。と言われて、単純な私は、そんなものかなあ・・。と納得しましたが、良く考えると、このあたりに、物つくり教育の大事な問題があるような気がしました。
モノを作るということは、人間の文化の根源です。どんなに技術が進んでも、あらゆるモノは、たとえ機械の手を借りているとしても、何処かで誰かが作っているのです。モノ作り立国という言葉が有りますが、実態はどうなのでしょうか。
考えなければいけない事は多いと思いました。